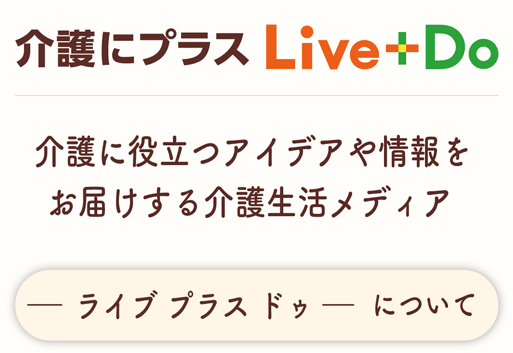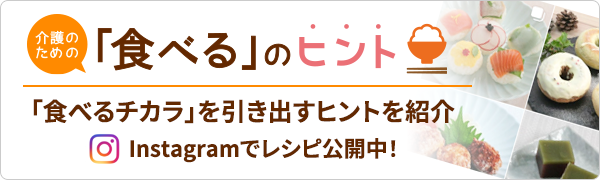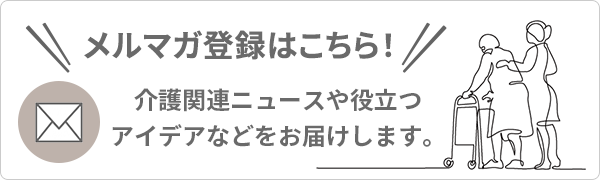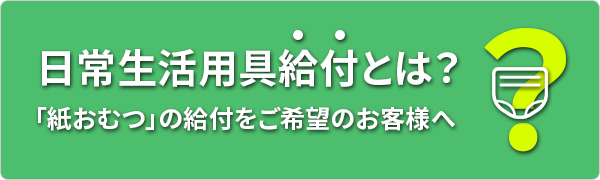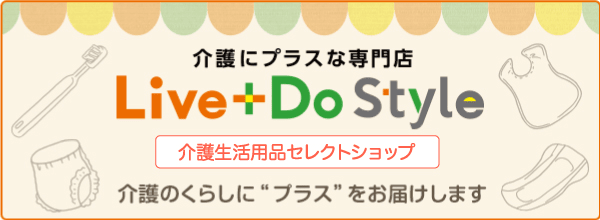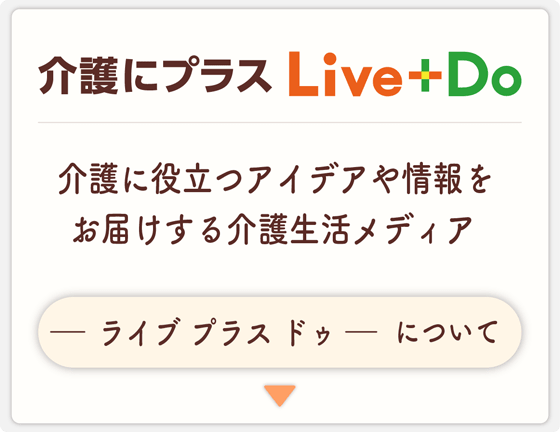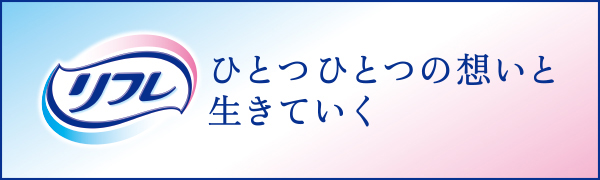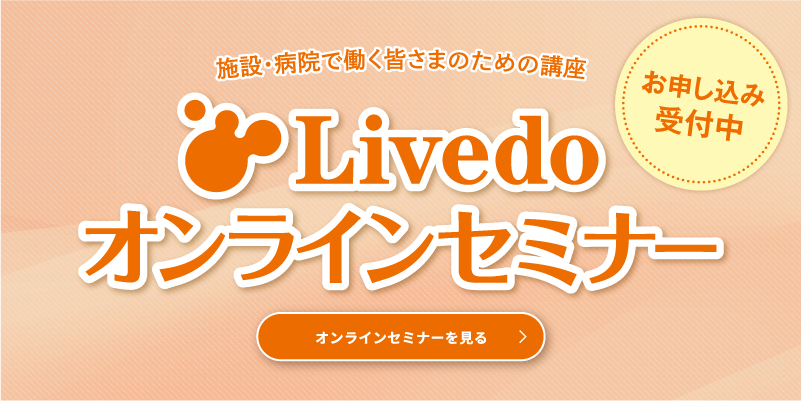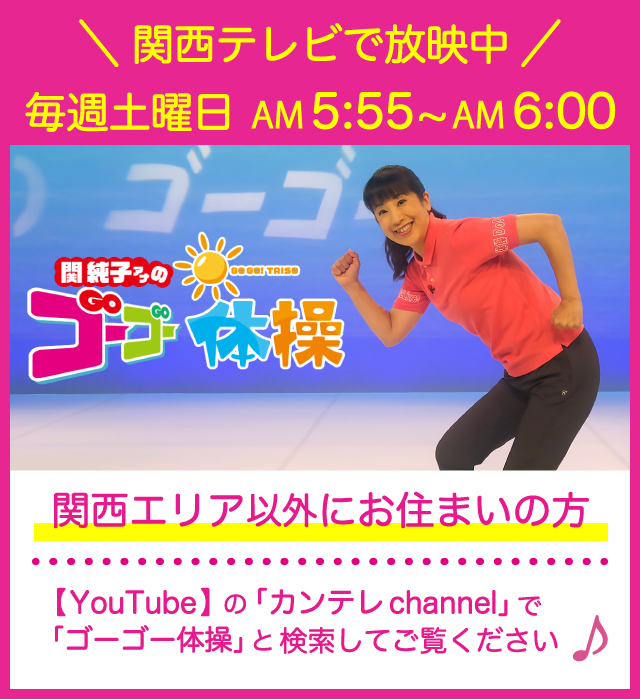口が開かない、噛みづらい…食べづらさのサインはありませんか?
身近にいる高齢者の方から「口が開きづらい」「食べ物が噛みづらい」といった声を聞くことはありませんか。開口力や咀嚼力の低下は食事量の低下にもつながり、栄養不足の原因になることも。このような状態の高齢者の方におすすめしたい食事として「ミキサー食」があります。今回はミキサー食について正しく理解し、少しでも食事がすすむ方法を一緒に考えてみたいと思います。
加齢や疾患が原因で、“食べるチカラ”は低下する
食事中の筋肉の動きは、口を開く、咀嚼中に唇を閉じる、食べ物を塊にする、喉の奥に送り込む、飲み込むなどがあり、安全に食べるための重要な連携プレーで成り立っています。口の開閉には咬筋と側頭筋が重要な役割を果たし、そのうち咬筋は食事を咀嚼するためにも欠かせない存在です。
ところが高齢者のなかには、さまざまな理由から口の開閉や咀嚼が困難になる方がいます。たとえば、脳血管疾患などの後遺症や何らかの障害がある場合、咀嚼(そしゃく)にかかわる神経や機能が低下するほか、咬筋などの筋肉を動かす指令がきかなくなり、食事そのものが難しくなることがあります。心身ともに健やかな方であっても、年を重ねるにつれて筋力が低下し、口を開ける力や咀嚼力の低下が見られるようになります。そのほか口腔環境に悪化によるものや認知症によって食べ方を忘れてしまうなど、理由はさまざまです。
食事介助のヒントになる「食べるメカニズム」とは?
食事量の低下で心配されるのが「低栄養」
口を開く力や咀嚼力の低下によって心配されるのが、食事量の低下による栄養不足、いわゆる低栄養状態です。生きるために必要なエネルギーや筋肉を作るたんぱく質が不足した状態をいい、筋力や身体機能が低下するサルコペニアや感染症を発症するリスクが高まってしまう原因となります。
噛む力・飲み込む力が低下した方に「ミキサー食」

ミキサー食は、見た目に立体感もなく、1つの献立を1食分まとめてミキサーにかけると、全体的に茶色っぽく彩りが悪くなって食欲を減退させてしまうことがデメリットです。また、水分が多いとすぐにお腹がいっぱいになってしまい、充分な栄養が確保できません。
ミキサー食とは
開口力や咀嚼力の低下によって食べづらさを感じている方におすすめしたい食事が、介護食のひとつである「ミキサー食」です。ミキサー食は、食材と出汁やスープなどの水分をあわせてミキサーにかけ、固形物をなくしてなめらかな状態にした食事のことをいいます。作り方の手順は次の通りです。
ミキサー食の作り方
❶ お魚やお肉などの固形の食材を用意する。
❷ ❶をスープやお出汁などの水分とあわせてミキサーにかけてかく拌し、ペースト状にする。
❸ 高齢者の食べるチカラに合わせて、とろみ剤や増粘剤などを使って硬さを調整する
ちなみに、ミキサー食によく似た食事としてペースト食があります。二つの食事に明確な違いはないのですが、介護食の分野では「なめらかで均質なもの」をミキサー食、「やわらかい粒などを含む不均質なもの」をペースト食と位置づけることが多いです*。
*参考:日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021
「栄養やカロリーの摂取量」「食べるチカラに合わせた硬さ」を意識して
ミキサー食は食べやすい反面、栄養価やカロリーの摂取量においては課題がある食事です。出汁やスープを加えてミキサーにかけると、その分食事の全体量が増えます。高齢者の多くは少食になっていますから、そのすべてを一度に摂りきることは難しいでしょう。そのため、本来の食事に含まれる栄養価やカロリーを十分に摂ることができず、栄養不足になってしまうことがあるのです。わたしが実際にミキサー食を作る場合は、かく拌に影響のない範囲内で、栄養価の高い食品を一緒にミキサーにかけています。たとえば、プロテインや油、牛乳などを加えることで、たんぱく質や脂質などを補うことができます。
もうひとつ大事なポイントとして、「硬さ(とろみ)」の調整があります。ミキサー食は水分を多く含む液体状のため、そのままではむせやすく、誤嚥につながる場合もあります。とろみ剤などを使用して硬さを調整しますが、「ちょうどいい」の基準は一概に言えず、高齢者の方それぞれで異なるものです。試行錯誤を重ねながら、高齢者の食べるチカラに適した「硬さ」を見つけ出すことが大切だといえます。
おいしく食べていただくためのひと工夫

食材ごとの彩りを残し、小皿に分けて盛り付けを
ひとつの献立を一食分まとめてミキサーにかけると、全体的に茶色っぽくなってしまいます。彩りが悪くなると、食欲を損ねてしまう場合があるため、器や盛り付けを工夫するのがおすすめです。赤や緑の食材をそれぞれ個別にミキサーにかけることで、鮮やかな色味を残すことができます。食材ごとに小皿に分けて盛り付けると、さらに見た目が華やかになります。
たとえば肉じゃがの場合…
お肉とジャガイモを先にミキサーでかく拌し、彩りとして残しておきたい人参やいんげんは個別でミキサーにかけます。一食分ごとにミキサーにかけるのは大変なので、多めに作るなどして手間をなるべく減らしましょう。
山芋やオクラ、豆腐…食材自体が持つ「とろみやねばり」を活かす
「とろみ剤に頼りすぎずに作りたい…」という方には、食材自体のとろみやねばりを活かした調理法がおすすめです。代表的な食材だと山芋やオクラなど、ねばねばしたものですね。たまごはやわらかなスクランブルエッグにしてからミキサーにかけると、ほどよいまとまり感を出すことができます。高齢者の食べるチカラの程度にもよりますが、お豆腐を活用することもおすすめです。適度に水分が含まれる豆腐は、水を加えなくてもそのままミキサーにかけられるため、栄養の面でも安心です。
とろみを活かすことができる食材
・山芋
・オクラ
・トマト
・たまご(スクランブルエッグ)
・はんぺん
・豆腐 など
スプーンの種類や姿勢の角度にも気を遣って

そのほか、使用するスプーンに工夫を凝らすことができます。形状でいえば、口に入れる部分が正円に近いものよりも、やや細長いしずく型のものがおすすめです。深さについては平たいものだと食事をすくいにくく、深すぎるものだと口に入れにくい場合があるため、浅めのものがいいでしょう。素材もやわらかなシリコン製や口あたりのやさしい木製などがあります。高齢者の方の口の大きさやお好みに合わせて選んでみてください。
また、食べるときの姿勢の角度も大切です。座って食事ができる場合は、なるべく背中を90度の状態に保ちましょう。座りながらの食事が難しい場合は、ベッドに横になり、60度程度(難しい場合は30度程度)に背もたれを起こしてください。いずれの場合もできる限り顎を引いた状態を意識することで、誤嚥が起こりにくくなります。
食材の彩りや旨味を活かしたミキサー食レシピ
あざやかな緑が食欲を刺激する
「えんどう豆のポタージュ」

さつまいもやかぼちゃでも代用できる
「冷製ポテトスープ」

出汁のきいた日本風ポタージュスープ
「すりながし」

食べる方の気持ちに寄り添いながら、安全で楽しい食事の時間を
口が開きづらい、噛むのが難しいといったようすが見られる高齢者の方には、一度ミキサー食を試していただきたいと思います。一般的な食事と見た目が大きく変わってしまうため、最初は抵抗を感じてしまう方も少なくないでしょう。栄養面の工夫はもちろんですが、毎日の食事だからこそ、どれだけ年を重ねても、おいしく食事を摂ることをあきらめないでほしいのです。盛り付けや彩りを工夫しながら、高齢者が安全かつ楽しみながら食事できる環境を作ること。その積み重ねが高齢者の低栄養の予防につながると思っています。