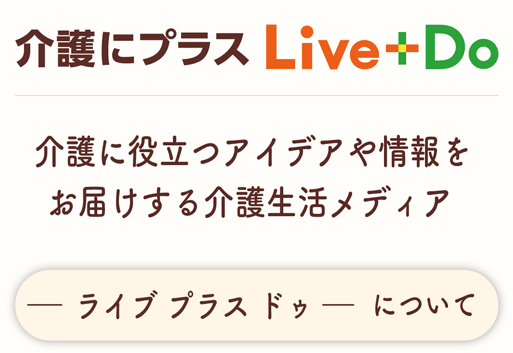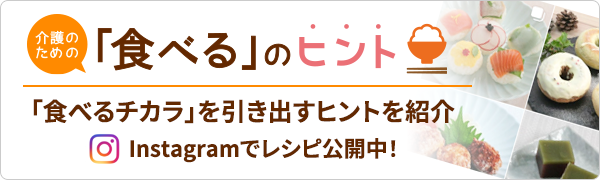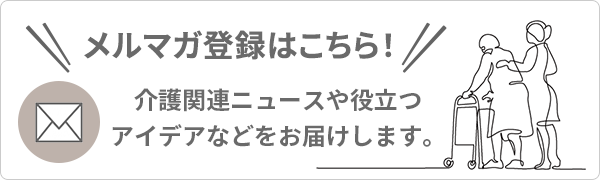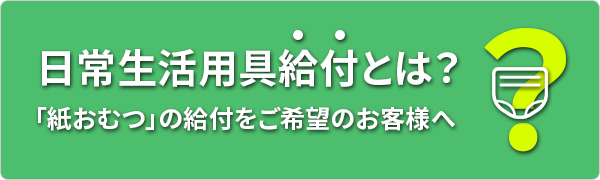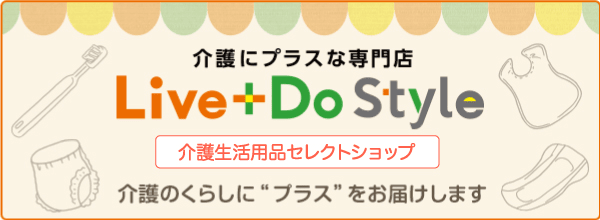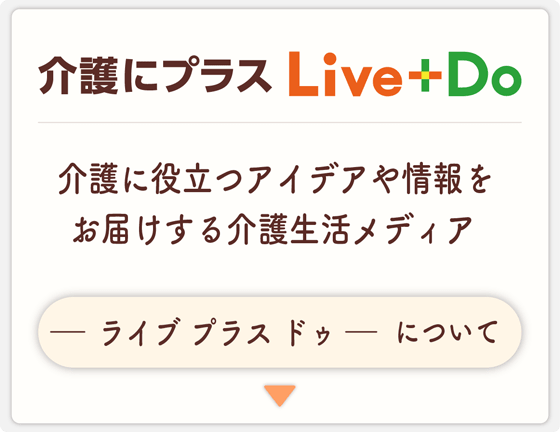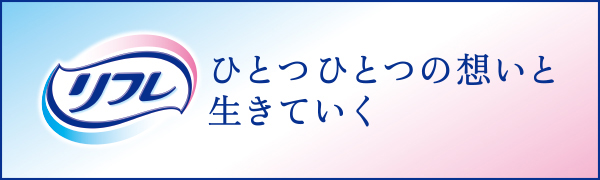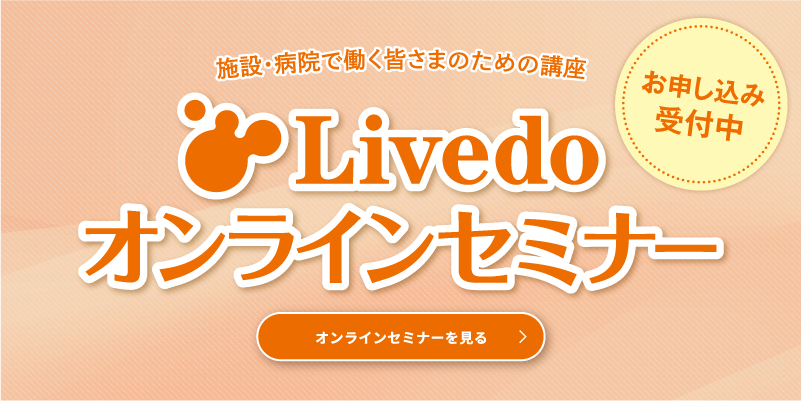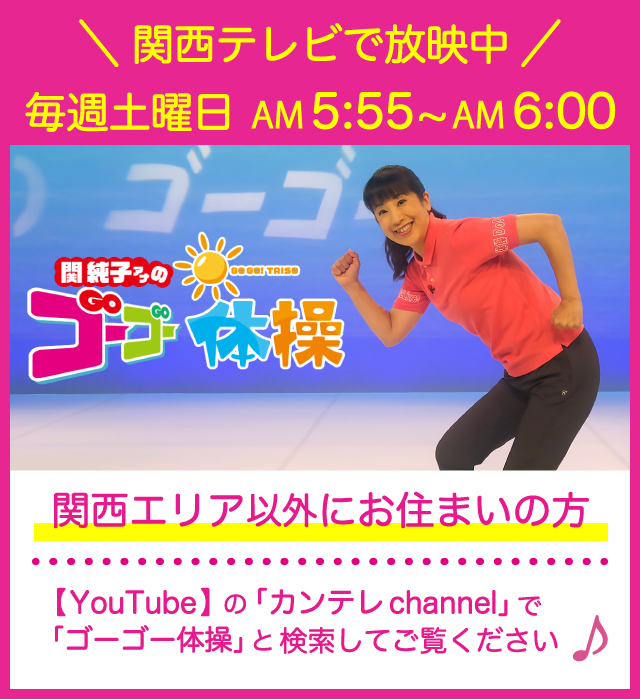梅雨も終わりが近づき、気温も高くなり始めた今日この頃。夏が本格的に到来する前に対策していただきたいのが、日々の水分補給についてです。特に高齢者の方は「喉の渇きを感じにくい」「トイレの回数が増えるから飲みたくない」などの理由で、水分の摂取量が減りがちに。気づかぬうちに脱水状態になってしまう危険性もあります。そこで今回は、水分が持つ役割や、高齢者の方に向けた水分補給の工夫についてご紹介したいと思います。
栄養や酸素の運搬、体温調節など…大切な役割を果たす「水分」

私たちの体重のうち約60%を占める水分ですが、そもそもどのような働きがあるのでしょうか。飲料や食事から体内に取り込まれた水分は、おもに血液などの体液となります。体外に出る場合は、尿、便、呼吸、汗となって排出されます。体液は絶えず体内をめぐり、栄養や酸素の運搬、老廃物の排出、体温調節などを行っています。このように、水分は人が健やかに生きていくために欠かせない存在といえるでしょう。
高齢者の1日の水分摂取目安量は「1500ml」
体内の水分が十分に役割を発揮できるよう、人には1日に摂るべき水分量の目安があります。高齢者の方が摂取すべき1日の水分量は、およそ2000~2500ml。そのうち、水分補給を通じて摂取すべき水分量は1500mlとされています。
高齢者の方は活動量が減るとはいえ、汗や呼吸、排尿や排便を通じて、自然と水分は身体から出ていきます。そのため、失われた体内の水分を補うためには、これだけの水分補給が必要なのです。とはいえ、1500mlという数字にはかなり大きく見えますよね。1日の水分補給の工夫については、のちほどお伝えしたいと思います。
高齢者が水分不足になりやすい理由

1日に摂取すべき水分量を知らなかったとしても、わたしたち成人の場合は喉の渇きを感じると、積極的に水分を口にします。一方で高齢者の方は、知らず知らずのうちに水分不足に陥っている場合があるのです。
のどの渇きを感じにくくなる
高齢者の方が水分不足になる理由として、「喉が渇く」という感覚が鈍くなることが挙げられます。これは、喉の渇きを感じる役割を持つ「口渇(こうかつ)中枢」の働きが、年を重ねるにつれて低下するためです。身体が水分不足を訴えていても、感覚として認知ができないため、水分補給の回数が減ってしまうのです。
筋肉量の低下により水分貯蓄が難しくなる
血液をはじめ、体内のあらゆるところに分布している水分は、筋肉内に多く蓄えられます。高齢者の場合は低栄養やサルコペニア(加齢により筋肉量が減少、筋力低下することをいいます)などにより筋肉量が減少するため、いつの間にか蓄えるべき水分量が少ない状態に。そうして、気づかないうちに脱水状態になってしまうことがあるのです。
ほかにも、トイレが近くなることやおむつの交換頻度を気にするため、水分補給を避けるという方もいらっしゃいます。
要注意!水分不足が原因で起きる「脱水症」

体内の水分が不足することにより、発症のリスクが高まるのが脱水症です。体内に必要な水分と電解質(塩分など)が足りない状態のことを指します。摂取する水分量が減少したり、汗や排尿によって体内から出る水分量が増えたりすることで、体内の水分量のバランスが崩れてしまい、脱水症が起こるとされています。暑くなるこれからの時期は、脱水症が引き金となり、体温の上昇や倦怠感を伴う熱中症にもつながりやすくなります。気になる症状が出た場合は、早めにかかりつけ医を受診するようにしましょう。
脱水症の際に見られる症状
・発汗
・発熱、微熱が続く
・嘔吐
・下痢
・めまい
・頭痛 など
脱水症によって発症するリスクのある病気
・熱中症
・脳梗塞
・心筋梗塞
・血栓ができやすくなる
・腎炎、急性腎不全 など
水分不足を防ぐ!高齢者のための水分補給法

脱水症をはじめ、水分不足による健康被害を防ぐためにはどうすればよいのか。その工夫を一緒に考えてみましょう。
高齢者のための水分補給法① 一日の摂取量を「見える化」する
ひとつめの工夫としては、1日に必要な水分補給の量を「見える化」することです。方法は、500mlのペットボトルを数本用意し、順次飲んでいくこと。その都度計量しなくても、どれくらい飲んでいるのかを把握しやすくなります。2ℓのペットボトルで用意すると、量に圧倒されてしまい飲み切ることに抵抗を覚えてしまうこともあります。飲んだ量が見えるだけではなく、飲むご本人も達成感を感じることができる小さなサイズのペットボトルがおすすめです。暑い日などは、お茶を少量のゼラチンと混ぜ合わせて冷やしておくと、喉の奥までスルスルと流れるように飲むことができます。飲みやすいジュースやスポーツ飲料など糖分を含むものは避け、喉が渇く前にタイミングをみながら補給するようにしましょう。
高齢者のための水分補給法② 汁物の料理から摂れる水分も合わせて、一日の摂取量をめざす
先ほど、高齢者の方が水分補給を通じて摂取すべき水分量は2000~2500mlとお伝えしましたが、正直「そんなに必要なの?」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。たしかに総合量でいうと途方もない量に感じられますが、この水分量は飲料だけでまかなう必要はありません。例えば、味噌汁やスープなどといった汁物の料理も1日の水分量にプラスして考えてはいかがでしょうか。塩分の摂りすぎには注意ですが、味噌汁ですと1杯約150mlの水分をとることができます。無理なく水分を補給する工夫として、「食事で補う」ことも、ひとつの工夫といえます。
高齢者のための水分補給法③ 「タイミング補給」を心がける
三つ目の工夫は、一日の行動に合わせて水分補給をおこなう「タイミング補給」です。目安となるタイミングは、起床時・朝食・昼食・夕食・入浴後・寝る前など。運動後や帰宅時、薬を飲む際でもよいでしょう。コップ1杯程度を約200mlとし、6~8回の行動に合わせて水分補給をすれば、一日の水分摂取量をクリアできます。それぞれのタイミングに合わせて補給する習慣をつけておくと、「飲まなきゃいけない」という気持ちの負担を軽減させながら、水分不足を防ぐことができます。
高齢者の水分補給のポイントや注意点

さいごに、高齢者の方が水分補給する際のポイントや注意点をお伝えします。
水分はこまめに摂る
水分補給で大切なのは、少ない量をこまめにとることです。一度に大量の水を摂ると、体内での処理が追いつかず、せっかく補給しても蓄えられないまま排泄されてしまいます。1杯200mlを目安に、何度かに分けながら水分補給するように心がけましょう。
日常生活は水でOK、活動的な日や緊急時には経口補水液などを
よく、「水分補給をする際は電解質(塩分)を一緒に摂ることが大切」と耳にすることがありませんか。これは汗を大量にかくことで、体内のナトリウムやカリウムがともに失われるためです。脱水症の“予防”の段階では、水を摂取するだけで十分です。特に活動量の低い高齢者の方の場合、電解質を含む飲料を飲むことで、かえって塩分過多になる場合もあります。ただし、長時間の外出やハイキングなど、汗をたくさんかくことが予想される場合や、先ほどお伝えした症状が出始めている緊急時などには、経口補水液など電解質が含まれる水分を摂るようにしましょう。
甘いジュースやコーヒーは水分補給に不向き
ジュースやコーヒーは高齢者の方にも人気の飲み物ですが、水分補給には適していません。糖分をたくさん含む甘いジュースは、飲むと血糖値が上昇し、身体がより多くの水分を欲しがる状態に。トイレの回数も増え、よりのどが渇いてしまいます。コーヒーには利尿作用のあるカフェインが含まれているため、体内の水分が不足し、知らない間に脱水症に陥る場合もあります。ジュースは嗜好品としておやつの時間に楽しむ、コーヒーは代替品としてノンカフェインを選ぶなどの工夫が大切です。
日々の水分補給を習慣にして、暑い季節も健やかに
今回は、水分の役割や大切さ、そして高齢者の方のための水分補給法についてお話しました。水分不足は命にかかわることもあり、「喉が渇いてから」では間に合わない場合もあります。これからの暑い季節を健やかに過ごせるように、日々の水分補給についてあらためて考えていただくきっかけになればと思います。