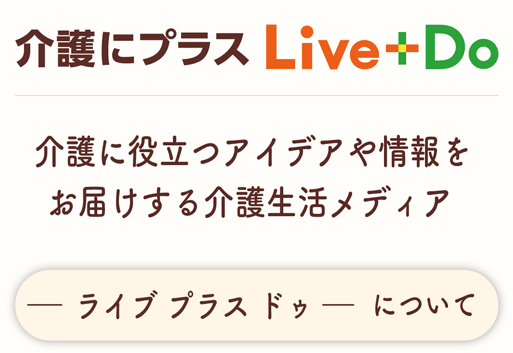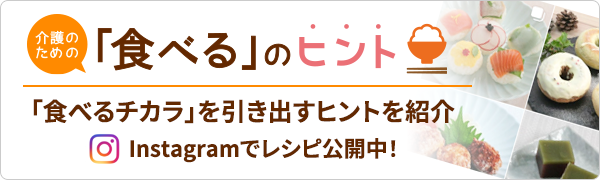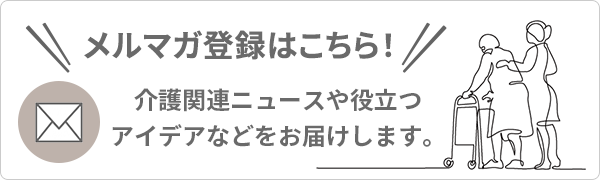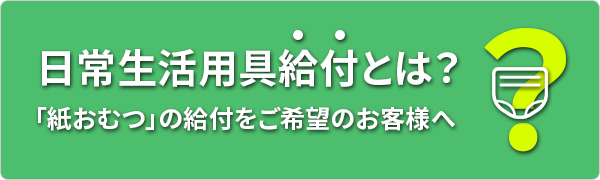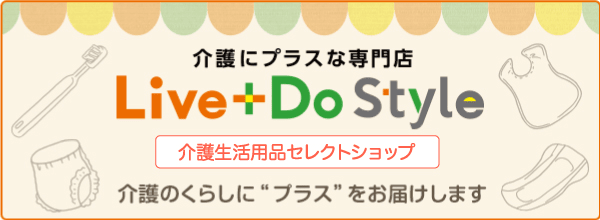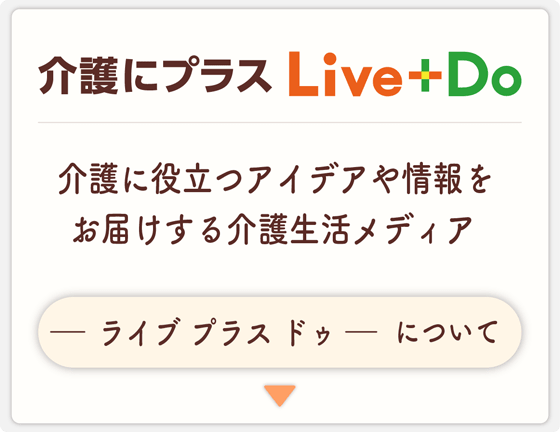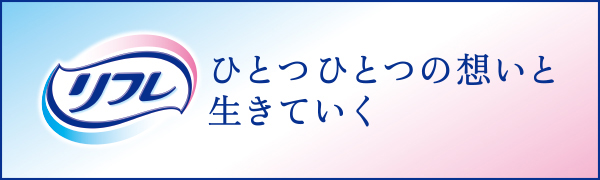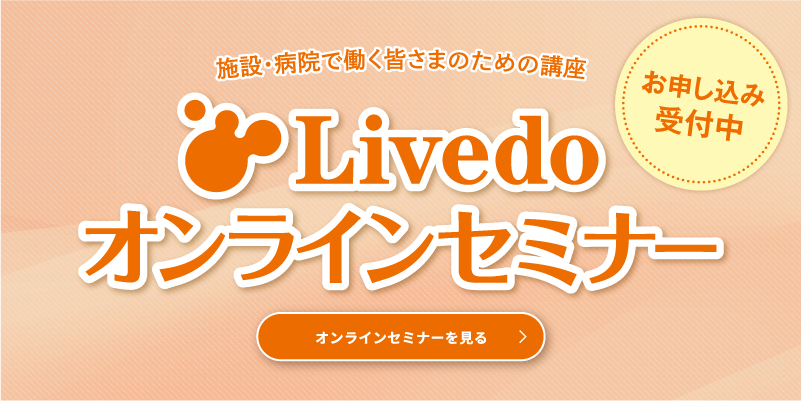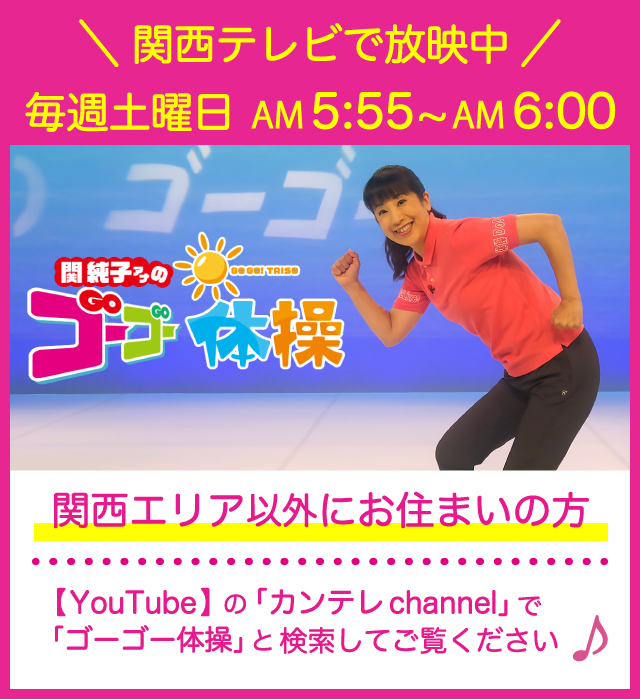みなさんは「唾液」の役割について考えたことはありますか?「この頃口の中がネバネバする」「前よりも味を感じづらくなった…」それらの原因の一つとして考えられるのが「唾液不足」です。口の中の唾液が減ると、口腔環境の状態が低下するほか、食事のしやすさに影響することも。今回は、唾液の役割や分泌量が減少する原因を知ったうえで、唾液分泌を促す工夫についてご紹介します。
おいしい食事をサポートする、唾液のはたらき

唾液にはさまざまな成分が含まれており、粘膜を保護・修復するはたらきや抗菌作用、再石灰化(歯の表面のエナメル質を修復する働き)など、口の中の健康を保つための重要な役割を担っています。
ほかにも食事と密接にかかわる機能があります。ひとつは「消化作用」。唾液に含まれるアミラーゼという消化酵素が、食べ物に含まれるデンプンを分解して胃の消化を助けます。つぎに「潤滑作用」。食べ物との摩擦によって粘膜が傷ついてしまうのを防ぐために、口にいれた食べ物を湿らせて、飲み込みやすくすることができます。さいごに「味覚作用」。舌の表面には「味蕾(みらい)」という味を感じるための小さな器官があるのですが、その味蕾に味を伝える媒介としての役割を唾液が担っています。普段の生活ではあまり気に留めない存在の唾液。実はとても大切な役割を果たしてくれているのです。
唾液が減ると誤嚥リスクを高めることも

ご紹介したはたらきも、唾液が十分に分泌されていることが条件で作用します。しかし高齢者の方の場合、唾液の分泌が低下しやすい傾向にあるのです。低下の原因はさまざまで、加齢や咀嚼力の低下、薬の副作用などが挙げられます。
~唾液分泌を低下させる主な原因~
*咀嚼力の低下(筋力の低下、歯の喪失、義歯や入れ歯の不具合など)
*薬の服用(抗うつ剤、鎮痛剤、降圧薬など)
*糖尿病や甲状腺に関わる疾患など
唾液分泌が減ってしまうと口の中の細菌が増えたり、歯周炎など歯ぐきの炎症が進行したり、口臭の原因になったりします。なかでも深刻なのが、誤嚥のリスクを高めるということ。口の中で食事をうまくまとめにくくなる、飲み込むために食べ物を喉の奥へ送り込みにくくなるなど、日々の食事に影響を及ぼす危険性があるのです。
口の中のネバつきが強く感じられるようなら、それは唾液減少のサイン。口の端に唾液が溜まったり、会話のしづらさを感じたりする場合も、唾液が少ないことによるものです。毎日の食事をたのしく、そして美味しくいただくために、唾液を増やすための方法を紹介していきます。
実践!唾液分泌を促す5つの工夫
①「うま味成分」を活用する
人には5つの味覚(甘味・酸味・塩味・苦味・うま味)がありますが、なかでも「うま味」は唾液分泌をたくさん促進させるはたらきあります。かつお節や昆布から作る「お出汁」には、うま味成分であるアミノ酸(おもにグルタミン酸)が豊富に含まれています。出汁を使った料理を献立に1品追加するなどして、唾液分泌にアプローチしてみましょう。
~おすすめレシピ~
「たらのつくね おろしあんかけ」

②「酸味」を活用する
梅干しを見ると唾液が“じわっ”と出てくるように、酸味にも唾液分泌を促すはたらきがあります。調味料の「酢」は唾液の分泌促進に加えて、食材をやわらかくするはたらきも兼ね備えています。咀嚼力が低下した方の食事には、ぜひ酸味を活用してみてくださいね。
~おすすめレシピ~
「豚肉と白菜の梅和え」

③よく噛む
唾液を増やすには、「噛む」という行為自体が重要です。食べ物をよく噛むことで唾液腺が刺激され、分泌を促すことができます。やわらかく食べやすいものばかりではなく、ゆっくりでも噛めるものを食事に取り入れるようにしましょう。
~おすすめレシピ~
「五目大豆」

④水分を積極的に摂る
唾液は99.5%が水分でできています。そのため、水分の摂取量が不足すると、おのずと唾液の分泌も低下してしまいます。水分といっても、「飲料水」のみと考える必要はありません。お味噌汁やスープなども水分のひとつと捉えてOKです。ほかにも、水分を多く含むトマトや大根などの食材を使ったり、とろみのあるあんかけ料理を食べたりするのもよいでしょう。
~おすすめレシピ~
「新じゃがのすり流し」

⑤食前に唾液腺をやさしくマッサージ
唾液は、顔の周辺にある「唾液腺」から分泌されます。唾液腺は耳下腺(じかせん/耳の下部)、顎下腺(がくかせん/顎から頬へ向かう部分)、舌下腺(ぜっかせん/顎の舌裏部分)の3つを指し、これらをマッサージすることで唾液の分泌を促す効果があります。マッサージのタイミングは食事前がおすすめ。やさしく気持ちいいと感じる程度に刺激しましょう。
❶耳下腺のマッサージ
親指以外の4本の指を頬にあて、奥歯のあたりから前に向かってグルグルと回す

❷顎下腺のマッサージ
左右の親指を顎の骨の内側の柔らかい部分に沿わせ、耳の下から顎の下にかけて押す。

❸舌下腺のマッサージ
両手の親指を揃え、あごの中心の内側を押し上げる。

画像引用:リハツバメ(https://zaitaku-st.com/)
唾液を増やして、健やかな食生活を
今回は唾液と食事の関わりとともに、唾液分泌を促す5つの工夫を紹介しました。これまで唾液そのものに関心がなかった方も、この記事をきっかけに興味をもっていただけたら嬉しいです。唾液促進をアップさせる工夫を日常に取り入れながら、健やかな食生活をお送りいただけることを願っています。