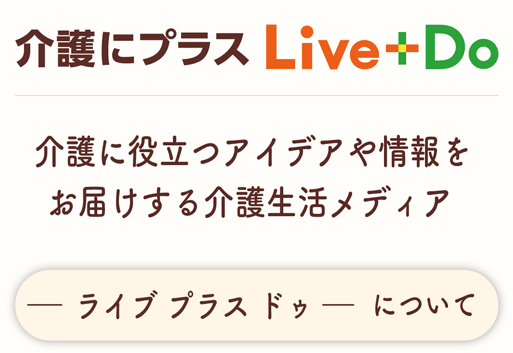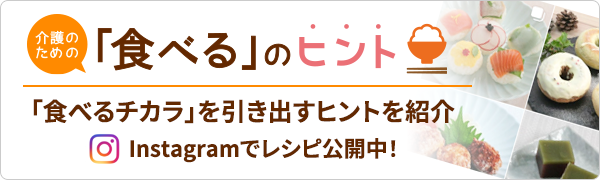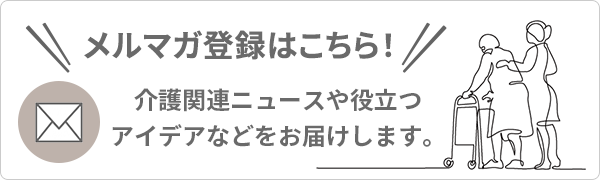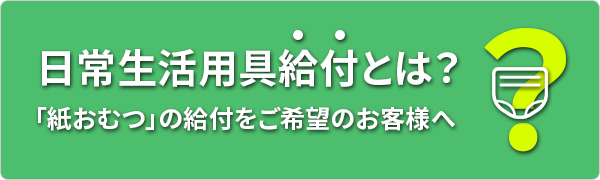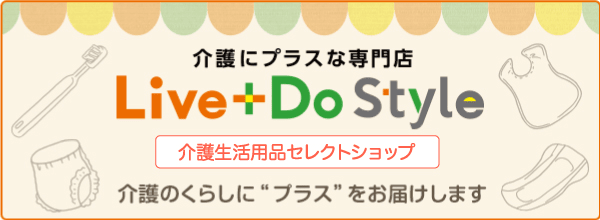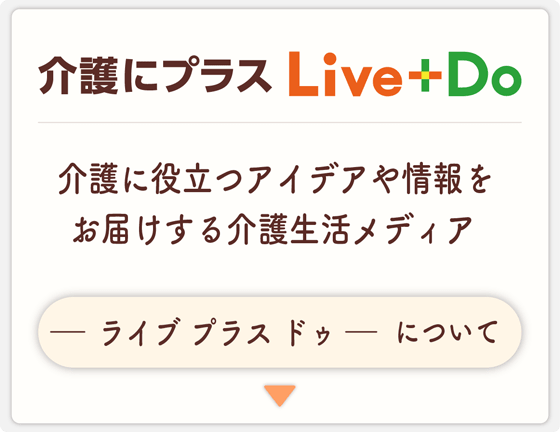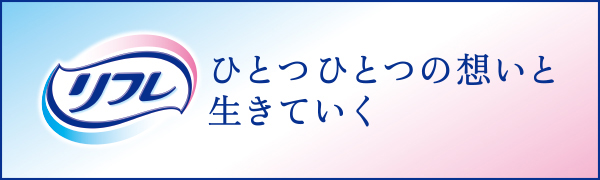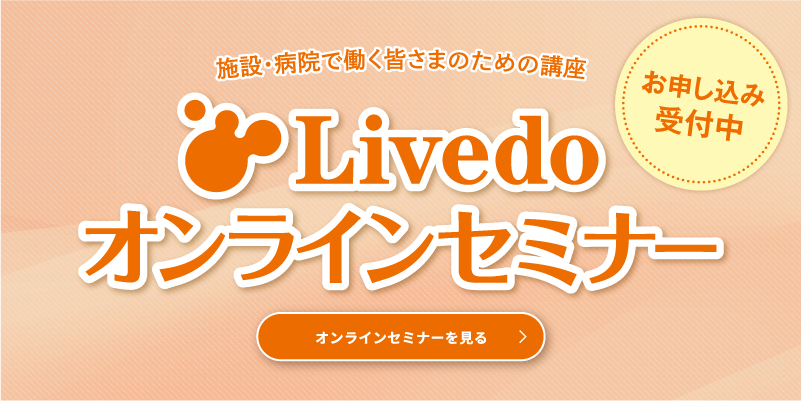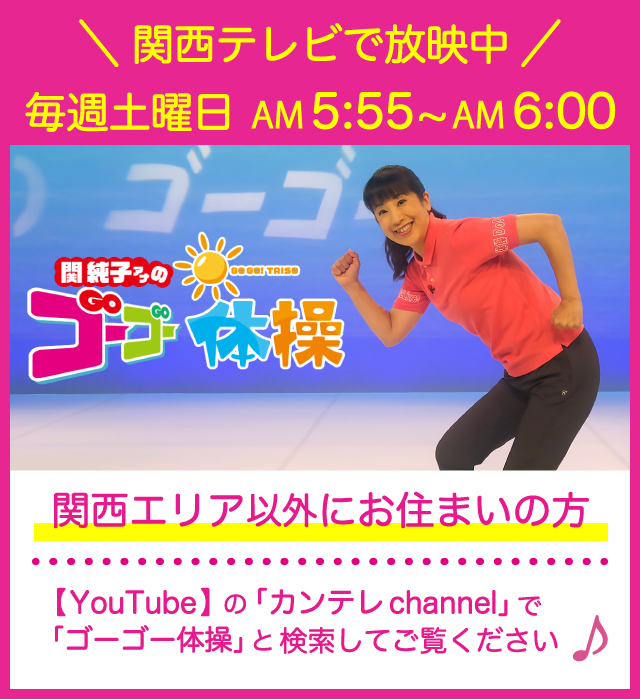家族と「同じ食事」を食べる幸せ

歳を重ねるにつれて、食べる機能が少しずつ低下していくことは避けられません。高齢者の方の姿を間近で見ているからこそ、やわらかく加工された介護食を提案するご家族もいらっしゃると思います。ところが高齢者の方の多くは、自分だけが違うものを食べていることに、寂しさや孤独を感じていることが少なくありません。
ご自宅や施設、どのような環境であっても「みんなで同じものを一緒に食べること」が私はとても大切なことだと思っています。いくつになっても食事を楽しめるという事実が、高齢者の方の気持ちを前向きにし、食への意欲を維持させることにもつながるからです。
「食べづらい」にどう向き合うか
とはいえ、高齢者の方にとって食べづらい食材や料理が存在するのも事実です。ものによっては誤嚥や喉の詰まりといった原因にもなりますから、やむを得ずメニューから外してしまうこともあると思います。
ただ、安全性に考慮してすべての食材を除いてしまうと、食べられるものはどんどん少なくなってしまいます。本来機能するはずの食べるチカラは次第に低下し、食に対する楽しみを失ってしまうこともあります。「食べづらそうだから出さない」ではなく、「食べづらいをどう食べやすくするか」。その工夫を考えてみてほしいのです。
高齢者の“食べづらい”を解決する工夫
食べづらいという感じることには、必ず理由があります。それぞれの食材の特徴を知ることで、解決の糸口は見えてきます。高齢者の方が好きなものを少しでも食べ続けられるように、その工夫をご紹介していきます。
「粘り気が強くて」食べづらいとき

お粥やいも類には独特の粘り気があります。ここで言う“粘り”とは、口の中にまとわりつくようなイメージです。やわらかさはあるけれど、喉の奥にへばりつき、水を含んでも飲み込みにくいため、誤嚥が起こる危険性もあります。この粘り気の原因は、食材に含まれる「でんぷん質」にあります。ミキサーで攪拌したり、冷ましたりすることで、独特の粘り(=糊化[こか])が生じます。
★ミキサーにかけたお粥には「酵素入りゲル化剤」を加える
お粥の粘りをおさえるのにおすすめなのが、でんぷん分解酵素を含むゲル化剤です。お粥特有の粘つきをおさえてゼリー状にしてくれるので、安全に食べることができます。メーカーによって適切な用量や攪拌回数、食材の温度が異なりますので、使用方法をよくご覧のうえご活用ください。
★じゃがいもなどのいも類は“熱いうち”に調理する
いも類は冷めてしまうと粘りが強くなる傾向にあります。調理の際は熱いうちにマッシュにする(煮たり、茹でたりしてすりつぶす)と、粘つきをおさえることができます。よりなめらかに仕上げたい場合は、牛乳や出汁などを加えてみましょう。
ちなみに、粘りを持つすべての食材が食べづらいわけではありません。納豆や長芋、オクラやとろろなどは、まとまりやすく食べやすいとされています
「パサパサして」食べづらいとき

次に、「パサパサする食べ物」。サワラや赤身のお肉、鶏のむね肉などは食材自体に水分や油分があまり含まれておらず、パサつきがちです。口の中でまとまりにくいため飲み込みづらく、残った欠片が気管に入りむせを起こす危険性もあります。
★水分や油分を加えた調理でしっとり感を出す
水分や油分が少ない分、新たに“加えることがポイント。加熱の工程で水分が残りやすい「蒸す」「煮る」「比較的低温でしっとり揚げる」などの調理法を取り入れてみましょう。「焼く」場合は、食材表面にマヨネーズなどの油分を加えることで、しっとり感を出すことができます。おすすめは、アルミホイルを使った調理。包み込んでじっくり焼くことで、食材自体に水分を閉じ込めることができます。グリルがない場合はフライパンでもOK。100円ショップなどで専用のアルミホイルが購入できます。
「ぺらぺら薄くて」食べづらいとき

「薄すぎる」食材にも注意が必要です。海苔やわかめなどは一見食べやすそうですが、ぺらぺらと薄いため、上あごに張り付いてしまうことがあります。
★細かく刻むか、代用品を使ってみる
そのままだと食べづらいわかめや海苔は、細かく刻めば食べやすくなります。味噌汁にはわかめの代わりにもずくを使う、巻き寿司には海苔の代わりに薄焼き卵を巻いてみるなど、代わりのものを使うのも一つの手です。
さいごに
高齢者の方が食べやすい食事を作るための第一歩は、「なぜ食べにくいのか」を知ろうとすることです。今回ご紹介したような「食材」によるものもあれば、高齢者ご自身の「機能」に課題がある場合もあります。その理由に寄り添うことで、工夫のヒントが見えてくるはずです。家族と一緒に同じものを食べること。その幸せをいつまでも感じていただくために、できることからぜひ始めてみてください。