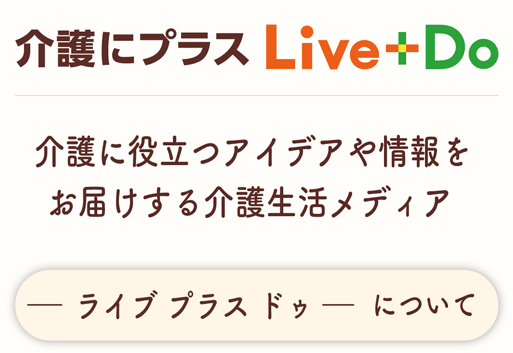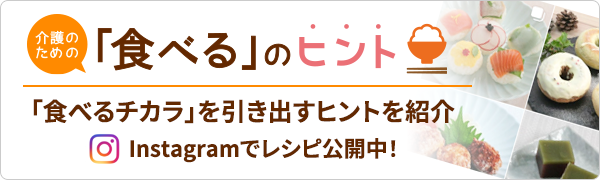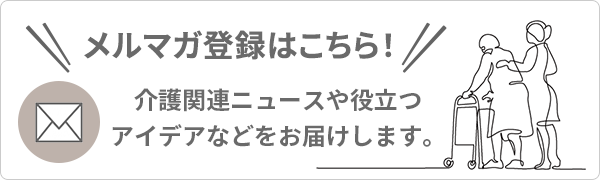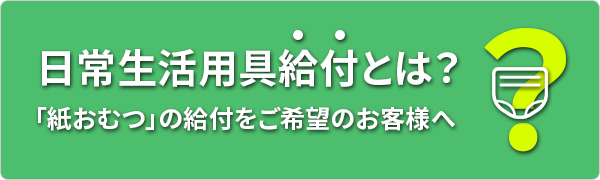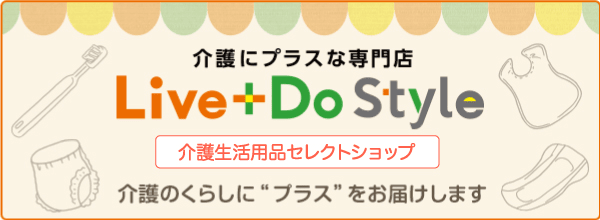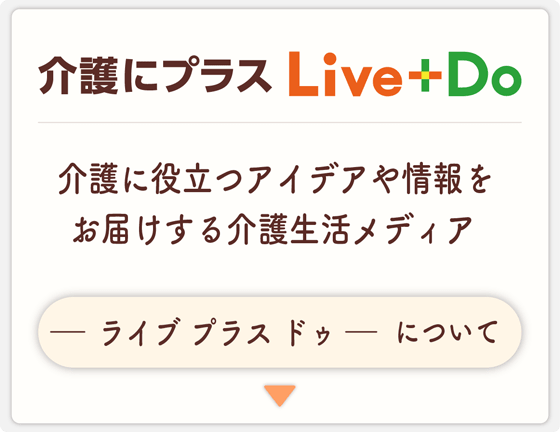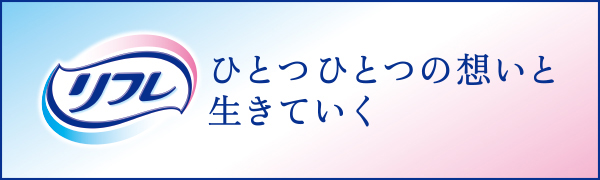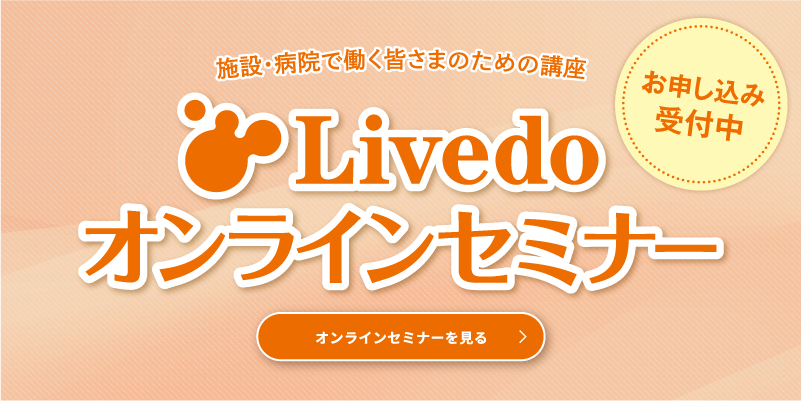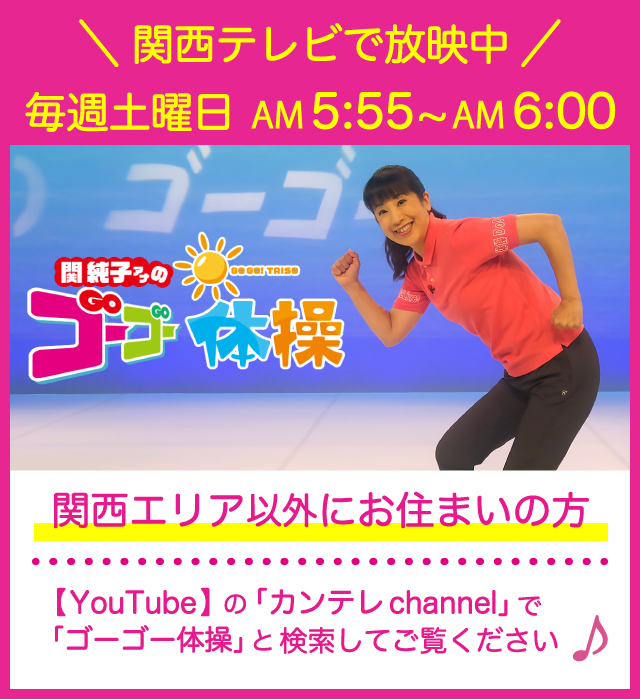「噛みづらくなった」「むせやすくなった」…など、年を重ねるにつれて食事の困りごとは感じやすくなります。一方で、見た目から伝わるほど柔らかい食事を摂るのはまだ早いと感じられる方もいらっしゃいます。高齢者の方の「噛むチカラ」に合わせた食事と、その力を維持させるためにできることを、今回は考えていきたいと思います。
噛むチカラとは
「噛むチカラ」というと、硬いものを噛みきる力だけをイメージされるかもしれません。口の中に入ってきた食べ物を咀嚼することはもちろん、細かくなった食べ物に唾液をからませてまとめる、食道のある喉の奥へと送り込む。これらすべてを「噛むチカラ」と呼んでいます。
噛むチカラを支えるのは唇や舌、歯に内頬、唾液などで、これらが連携しあうことで食べるという行為が成り立っています。このうち1つでも機能が低下すると、食べづらいと感じるようになります。
“食べる”に欠かせない「唇・舌・歯・内頬・唾液」
◎唇
「とらえる」…上唇と下唇で食べ物を挟んでとらえる
「閉じる」…食べ物や咀嚼音が外へ流れ出るのを防ぐ
◎舌
「まとめる」…細かくなった食べ物を攪(かく)拌し、一つの塊(食塊)にする
「送り込む」…食べ物を喉の奥へと移動させる
◎歯
「噛む」…口の中に入った食べ物を上下の歯ですり潰して粉砕する
「固定する」…食べ物が口内から出ていかないようにおさえておく
◎内頬
「固定する」…食べ物がこぼれ出ないように固定する
◎唾液
「まとめる」…消化酵素を含む粘液で食べ物に粘りを持たせ、まとまりやすくする
・食事介助のヒントになる「食べるメカニズム」とは?
心身にも影響を及ぼす「オーラルフレイル」

冒頭でお伝えしたとおり、噛むチカラというのは、加齢に伴い多少なりとも衰えはじめます。その衰えを対処しないままでいると、「オーラルフレイル」に陥ることもあります。オーラルフレイルとは、「オーラル(oral)=口腔の」「フレイル(frail)=虚弱」とあるように、口腔機能の低下が全身にも悪影響を及ぼす状態のこと。
つまり、噛むチカラは身体への健康状態にも大きく関わっていると言えます。口内状況を知るきっかけづくりの一つとして、専門機関によってセルフチェック表なども作成されています。気になる方は、かかりつけの歯医者さんにご相談いただくのもいいかもしれません。
大切なのは、今ある「噛む力」を使うこと
オーラルフレイルを防ぐためにはどうすればいいのか。それは、今ある「噛むチカラ」を使い続けることです。歯を使わなくてよいほど柔らかかったり、ツルンと楽に飲み込めたりたりする食事は、確かに食べやすいでしょう。けれど、その食べやすさがかえって食べるチカラを弱めてしまう原因にもなります。
適度に噛みやすく、柔らかすぎない料理のレパートリーを増やすこと。これが、噛むチカラを維持するために大切なことなのです。
見た目からはわからない、噛む力を活かす“ひみつの”工夫
今回お伝えする、食べるチカラを使うための調理の工夫。それは、一見どこに変化を加えたかわからない“ひみつの”工夫です。目指すのは、「いつもの食事と変わらないのに、今日は食べることができた!」と、高齢者の方に感じていただくこと。「食べやすく作ってみたから、ぜひ食べてみて!」と言いたい気持ちを少し我慢して、こっそりと工夫を加えていただけたらと思います。
①異なる食感を組み合わせて、咀嚼力をきたえる
咀嚼力を強くするためには、異なる食感を組み合わせるのがおすすめです。比較的噛みやすい食材と噛み応えのある食材を混ぜ合わせることで、咀嚼力が分散され、噛む回数を自
然に増やすことができます。また、野菜の皮をすべて剥かずにあえて残すことで、硬めの食感とやわらかな食感を同時に出すことができます。
たとえば…
・「キャベツ」と「ニンジンの千切り」
・「ひじき」と「大豆」の煮物
・きゅうりなどの皮をピーラーで縦に交互に剥く(見た目も美しく仕上がります)

②包丁の使い方を工夫する(繊維を断つ/隠し包丁)
野菜のシャキシャキ食感は、咀嚼力が低下している場合には少し食べづらいこともあります。そんなときは、繊維を絶ち切るように包丁を入れることで噛みやすくなります。ま
た、素材に切り目を入れる「隠し包丁」も噛みやすさにつながるテクニックのひとつです。白身魚のお刺身などにも、隠し包丁を入れることで食べやすくなるはずです。
たとえば…
・お刺身は裏面に2~3 か所の切れ目を入れる
・エビは色の境目に沿って切れ目を入れる
・野菜は繊維の流れに対して垂直に包丁を入れる

③「つなぎ」になる食品を使う
口の中の食べ物が上手にまとまらず、飲み込むまでに時間がかかってしまう…。それは唾液の分泌が十分ではないために、口内がパサパサした状態になっているからかもしれませ
ん。そんなときには、豆腐や里芋など、食べ物をまとめる役割を担ってくれる「つなぎ」となる食材を使ってみましょう。
④(飲み込む)とろみをつける
飲み込みづらい場合は、食事に程よいとろみを加えることで、喉の奥へとスムーズに送り込むことができます。くず粉や片栗粉でつくったあんや、マヨネーズなどとろみのある調
味料を加えることで、飲み込みをサポートしましょう。
たとえば…
・くず粉や片栗粉で作ったあんをかける
・マヨネーズやケチャップなどのとろみのある調味料を使う
さいごに
今回は「噛むチカラ」を使うための工夫を紹介しました。食べられる食事が増えれば、高齢者ご自身の自信にもなりますし、オーラルフレイルや介護の予防にもつながります。食に対する意欲を失うことなく、自らで咀嚼し、飲み込み、味わう。そうして日々の食事を楽しむことができるようにしたいですね。
参考文献:咀嚼の本(日本咀嚼学会)